天井埋め込みエアコンを使用している家庭は少ないかもしれません。
しかし、これからマイホームを建てる人は天井埋め込みエアコンを検討しているのでは?
- 生活感が出てしまうエアコンはなるべく目立たせたくない
- 天井埋め込みエアコンの使い心地が知りたい
我が家はダイキンの「家庭用 天井埋め込みエアコン(ビルトインエアコン)」を導入しました!
実際に使用してみたレビューも交えながら、メリットやデメリットについて解説していきます。
天井埋め込みエアコンを検討中の人は必見だよ!
間取りに不安がある方や、まだ間取りが決まっていない方こそ、無料でプロに相談してみましょう。
我が家は10通りほどの間取りを入手!
間取りのレパートリーを増やすことで、視野が広がりました。
天井埋め込みエアコンのメリット7選

我が家が実際に感じている、天井埋め込みエアコンのメリットは以下の通りです。
- 壁面スペースが確保できる
- 見た目がスッキリする
- 空気の循環がよくなる
- 配管が隠せる
- 電気代の節約になる
- 音が静か
- 自由な部屋のレイアウトが可能
それでは、1つずつ詳しく解説します。
1. 壁面スペース確保
天井に設置することで、壁面スペースを確保できるため、壁面家具や壁掛け装飾品を配置しやすく、広々とした空間を作り出すことができます。
我が家の場合は壁面を有効活用して窓を設置することができました。
両隣に家がぴったり建っているため、採光が取りにくい我が家。

天窓(トップライト)頼りになってしまうため悩んでいましたが、壁面スペースを確保できたことによって、天窓以外の採光を確保することができました。
我が家の天窓事情については上記で詳しく紹介しています。
2. 見た目がスッキリ
天井埋め込みエアコンは、床や壁面に設置するタイプと比べて、見た目がスッキリしています。
我が家の場合はクロスがホワイトなので、エアコンのカラーもホワイトを採用しました。
同系色にすることによって、統一感もあるため気に入っています。
そして、天井からの厚みもほとんどありません。

部屋全体がすっきりとした印象になるね!
3. 空気の循環がよくなる
天井に取り付けることで、空気の循環がよくなり、広い範囲に風を届けることができます。
吹き抜けのある部屋にエアコンを設置しましたが、効きが悪いとは特に思いません。
吹き抜けのある家は冬が寒い!とよく耳にしますが、杞憂だったと感じています。
さらに嬉しい誤算も!
我が家は16.5畳のリビング階段ですが、2階の部屋の扉を開けておくと、2階のエアコンを稼働させなくても十分暖かいです。
2階の寝室には壁面に設置する「ごく普通のエアコン」がありますが、大寒波で騒がれた2023年1月でさえ稼働することはありませんでした。
ゆえに、部屋全体に風を行き渡らせ、空気の滞りを解消することができると言えるでしょう。
LDK16畳については上記で紹介しています。
4. 配管が隠せる
天井埋め込みエアコンは、壁面や床に比べて、ダクトや配管を隠すことができます。
見た目的にも、配管があるのとないのでは違いますよね。
さらに、隠れた配管分のスペースを有効活用することができます。
ホテルライクな家を目指していたから、生活感をなくしたかったんだ!
ホテルライクな家を目指している人は上記も参考にしてみてくださいね。
5. 電気代の節約
天井埋め込みエアコンは、省エネ性に優れているため、電気代の節約につながります。
また、暖房を使用する際は風量は自動にしたり、風向きを下にするといった工夫をすることで、快適な空間を維持することができます。
冬は2階まで暖かいくらいパワフルなので電気代を心配していましたが、賃貸アパート暮らしのころと大差がなかったため安心しました。
どうなるか不安だった電気代も、杞憂だった〜!
我が家の電気代については上記で赤裸々に紹介しています。
6. 音が静か
天井埋め込みエアコンは、静音性にも優れています。
音に敏感な人や、寝室などの静かな場所でも使いやすいと思います。
パワフルなのに以外と静かで驚いたよ!
7. 部屋のレイアウトが自由
天井埋め込みエアコンは、設置場所を選ばないため、部屋のレイアウトに合わせた自由な配置が可能です。
また、家具や装飾品との調和も取りやすいです。
こんなにメリットがあるんだね!!
天井埋め込みエアコンのデメリット
天井埋め込みエアコンのデメリットは2つあります。
- コストがかかる
- メンテナンスが困難
後悔する前にあらかじめデメリットについても理解しておきましょう!
コストがかかる
設置には工事が必要で、取り付ける場所によっては天井を開ける必要があり、コストがかかることがあります。
部屋の広さにもよりますが、20万円前後の予算を見ておくとよいでしょう。
我が家は少しでも費用を抑えるために、インターネットで購入して施主支給しました。
施主支給については上記で詳しく紹介しています。
施主支給を検討中の人は上記もチェックしてみてくださいね。
とはいえ、壁面に設置するエアコンも性能によっては、そこそこのお値段がしますよね。
これから新築やリフォームなどを検討している方は、7つのメリットの観点から早い段階で導入することをおすすめいたします!
メンテナンスが困難
メンテナンスがしにくく、修理が必要な場合には、天井を開けなければならないため、コストや手間がかかることがあります。
我が家はメンテナンスを考慮して、天井裏から点検に入れるようにしてもらいました。
設計の段階で、天井埋め込みエアコンを採用したいと考えていたため設計しに考慮いただきました。
前向きに検討するなら早い段階で!だね。
天井埋め込みエアコンを採用するなら間取りの段階で検討!
初期費用がかかるものの、部屋の空間をスッキリさせたい方には天井埋め込みエアコンがおすすめです。
採用を前向きに検討するのであれば、間取りを決める段階で進めていきましょう。
間取りに不安がある方や、まだ間取りが決まっていない方こそ、無料でプロに相談してみましょう。
- 視野の広さと経験に基づく設計ができる
- ライフスタイルに合った設計ができる
- プランの可視化ができる
- コストの削減ができる
- 法令や規制に対応した設計ができる
「間取りのたたき台として活用」することや、「セカンドオピニオンとして活用」することが可能ですよ。
間取りは複数の視点から作成できるとよいでしょう。
すでに間取りをもらっている方は、異なる視点で考えてもらうことができます。
これから間取りを検討するという方は、無料なので気軽に相談してみましょう。
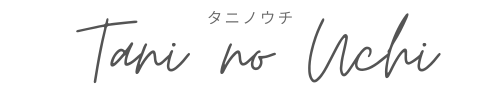
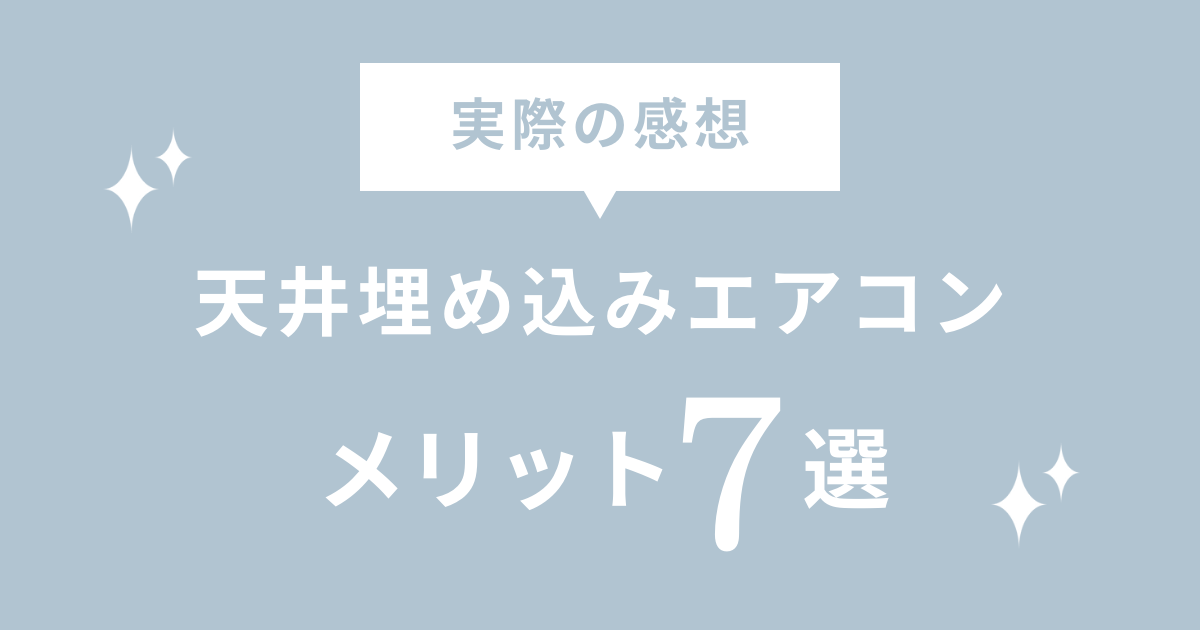

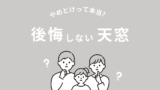


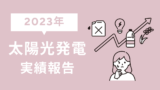

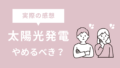
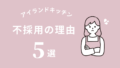
コメント